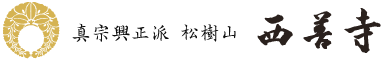2026年2月の法話
|
[2月の法語] |
|
一切衆生の救われる道でなければ 自分は救われない |
|
If thre is not a way to save all life, then there is no way for me to be saved. |
|
金子 大榮 |
[法話]
この法語に見られる「自分」という言葉には、大きく分けて二つの立場を想定できます。そして、その立場によって法語の意味も少し変わってくるような気がします。
一つは、親鸞聖人が非常に大切にした『仏説無量寿経』という経典に出てくる法蔵菩薩の立場です。法蔵菩薩はのちに阿弥陀仏と成りますが、成仏する前に生きとし生けるもの(一切衆生)を救う願いを立て、「願いが実現しなければ自分は仏に成らない」と誓います。これは、法蔵菩薩にとって一切衆生の救済が成仏の絶対条件であることを意味します。
つまり、法蔵菩薩の立場から言えば、この法語は「あらゆる存在が救われないことには「自分」も救われない」という断固たる決意、あるいは救いの構造を表す言葉になります。
もう一つは、「煩悩具足の凡夫」と言われるような、自己中心的な欲望に縛られて生きる平凡でありふれた者の立場です。親鸞聖人は、まさしく自分が「煩悩具足の凡夫」であることを自覚して、ただ念仏すること以外に助かる道はないと言います。それは「いずれの行もおよびがたき身」と言われるように、いかなる修行も「煩悩具足の凡夫」には成し遂げ難いことを痛感したからに他なりません。特に念仏以外の修行は個人の素質や能力を当てにするため、「煩悩具足の凡夫」を救えるだけの平等性・普遍性(ふへんせい=すべてのものに通じる性質。また、広くすべての場合にあてはめることのできる性質)を持ち得なかったのです。
このように、少なくとも親鸞聖人が立った「煩悩具足の凡夫」の立場から言えば、「あらゆる存在に平等普遍に成り立つ道でなければ「自分」という存在は救いようがない」とも読めます。
そもそも、金子氏が表題の言葉を語った文脈では、明らかに前者の意味です。金子氏は、美しい花を愛でるにも、その感動を共に分かち合う相手がいなければ美しさを味わえないことを例に挙げ、喜びや悲しみは決して個人的な問題に収まらないのだと言います。
確かに私たちは日常の様々な場面で、喜びを共有できる相手が多いほど、より大きな喜びを感じたことがあるはずです。また、悲しみの原因がより多くの人に関わるものであるほど、より深刻に感じられたこともあるでしょう。その意味で、「自分」一人の救いを良しとしない一面は、誰しも本来的に持っているのかもしれません。
しかし一方で、状況次第で「自分さえ良ければ」と自分本位の考え方を優先することも少なくありません。それどころか他人の失敗や不幸を喜ぶことさえあります。このことは、私たちにとって「他人の不幸は蜜の味」という言葉が聞き慣れたものである程度には、心理的傾向として往々(おうおう=しばしば)に有り得ると言えるでしょう。
そこであらためて法蔵菩薩の立場で考えてみると、私たちは「一切衆生」と呼ばれる救いの対象をどこまで押し広げることができるでしょうか。家族や友人ならともかく、悪の限りを尽くしてきたような人、さらには人類以外の生き物はどうでしょうか。そしてこのように考えていくと、私たちは救われるべきでない、あるいは、その救いに無関心な存在にどうしても思い至るのではないでしょうか。
ここに私たちの考えるべき方向の転換点があります。思えば親鸞聖人は、まず自分自身がどのような人間なのかに目を向け考え直した人でした。すると見えてきたのはどうにも救いようのない「煩悩具足の凡夫」、「いずれの行もおよびがたき身」としての「自分」です。しかしだからこそ親鸞聖人は、その「自分」をも救おうとする法蔵菩薩の願いを全存在の内なる願いとして聞き、そこに確証された世界を「一切衆生の救われる道」として示し続けたのでしょう。
松岡 淳彌(まつおか じゅんじ)
1990年生まれ。大谷大学任期制助教。
九州教区長崎組安樂寺衆徒。
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註]金子大榮:(1881~1976)日本の明治~昭和期に活躍した真宗大谷派僧侶、仏教思想家。前近代における仏教・浄土真宗の伝統的な教学・信仰を、広範な学識と深い自己省察にもとづく信仰とによって受け止め直し、近代思想界・信仰界に開放した。

2026年1月の法話
|
[1月の法語] |
|
み教えによって自分のありのままの相が知らされるのです |
|
The teachings show us a way to see ourselves in a true light, as we really are. |
|
藤田 徹文(ふじたてつぶん) |
[法話]
この法語は、藤田徹文著『はじめて仏教を聞く人のための13章』(本願寺出版社)の「信心」という章に記された言葉です。
藤田師は、「今の若さも、健康も、生命も、確かなものではありません」、「信用できないものを信用できると思いあやまって、自分に固執(こしゅう=自分の意見などをかたく主張してまげないこと)して、結局、自己と人生の方向を見失っているのが私たちではないでしょうか」と述べられています。そして、仏の教えによって、普段、頼りにならないものを頼りにしている「ありのままの自分」があきらかになり、さらには「本当に確かなものは「どんなことがあっても、あなたを見捨てることのない私がいます」と呼びつづけてくださる阿弥陀如来であったということが審らか(=物事の細かい点まで詳しく、はっきりとわかる様子)になる」と記されています。
私はこの法語と文章を読んで、中国の善導大師の言葉を思い出しました。
経教はこれを喩うるに鏡のごとし、しばしば読み、しばしば尋ぬれば智慧を開発す。
(『観経疏』『真宗聖教全書』第一巻493頁)
これは「仏の教えは鏡のようである。しばしば読んで、しばしば尋ねていくと、智慧を開き発す」と、仏の教えが鏡として喩えられ、そして、その鏡によって仏の智慧の眼が私の上に開かれてくるということです。
み教えの鏡によって映し出されるのは、自分自身の心の相です。それは、世間の価値観と自分中心の思いとで、どこまでも偏った見方で人や物事を受けとめてしまう私の相です。そして、思い通りにならない現実まで、どうにかして自分の思いどおりにしようともがき苦しんでいる、そのような無明(むみょう=道理に暗い)の私の相があきらかに知らされるということでしょう。
私は以前、高齢者施設で相談員をしていました。たくさんの人生の先輩方と日々を共にする中で、さまざまなことを学ばせていただきました。その一つは、私たちは人生の終わりが近づくにつれて「自分の人生を、どう受けとめていけばよいのか」という問いが、折に触れて湧き起こってくるということです。なかには、人生をどうしても否定的にしか受けとめられないという方も、少なからずいらっしゃいました。
私たちの人生は、自分の思いや計だけではとても受けとめきれないような様々な出来事が起こります。
仏の教えの鏡によって、私に開き発る智慧の眼は、「逃げ出したくなるような病気も、老いも、つらい様々な出来事も、すべてかけがえのない尊い私の人生なのだ」と受けとめることができない私たちを、ありのままに見つめる仏の眼です。言いかえれば、それは自分の思いをはるかに超えて、私の人生をまるごと引き受けてくださる阿弥陀如来のお心なのでしょう。
阿弥陀如来は、自分の人生の出来事をなかなか承知できないでいる私の思いをよくよく知ってくださっていて、そのような私たちに、全てを引き受けていける智慧の眼が開き発ることを本当に願っているのです。
私たちの生活の中では、いつでも、どこにいても、ありのままの私を映し出す鏡のはたらきが「南無阿弥陀仏」のお念仏であるといえるでしょう。
中島 航(なかじま こう)
1975年生まれ。九州大谷短期大学准教授。京都教区山城第2組浄泉寺衆徒。
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註]藤田 徹文:1941~2024 大阪市生まれ。龍谷大学大学院(真宗学専攻)修了。本願寺派基幹運動本部事務室部長、浄土真宗本願寺派伝道院部長・主任講師を経て、備後教区光徳寺前住職、本願寺派布教使

今年の法話(2026年)
|
[今年の法語] |
|
これからが これまでをきめる |
|
How I live from now reveals how I have lived until now. |
|
藤代 聰麿(ふじしろとしまろ) |
[法話]
どんな家に生まれたか。どこの学校を出たのか。どんな職場で、どんな地位にいたか。どんな資格を持っているか。社会における人間の評価は、およそ履歴書で判断されます。学歴や、経歴を誇れる人は、世間の期待を受け、大手を振って道を歩けますが、誇れる学歴も経歴もなく、つらい過去を持つ者は、差別に満ちた格差社会の中で、耐えて生きるしかない現実があります。世間の常識から言えば、「これまでが、これからを決める」のでしょう。
しかし、よくよく考えてみると、もし、履歴書によって未来のすべてが本当に決まるのなら、優等生しか助からないことになり、仏教が目指す万人平等の救いは、成り立たなくなってしまいます。
親鸞聖人は、『教行信証』「行巻」(聖典第二版209頁)に、「大小聖人、重軽悪人、皆同じく斉しく選択大宝海に帰して念仏成仏すべし」と、示しておられます。偉大な聖者も、立派な人も、極重悪人も、ちっぽけな悪人も、助かる道は、ただ一つ、如来が選択して下さった功徳の大宝海に帰して、念仏して仏に成る道しか無い、と示しておられるのです。
『正信偈』には「等覚(とうがく=等正覚))を成り、大涅槃を証することは、必至滅度の願成就なり」と謳われています。すべての衆生が等正覚(とうしょうがく=如来に等しい覚り)を成り、大涅槃を証することが出来る根拠は、個人の努力にあるのではなく、如来が必至滅度の願(=浄土往生した者に必ず仏のさとりを得させるという願い)を成就して下さったからだ、と示されました。
人生は、過去で決まる、と思い込み、過去を悔い、現在を苦しみ将来はどうなるのだろう、という、誰もが抱いている不安を、根底から払拭して下さったのが、親鸞聖人の先のお言葉です。
自力を頼み過去の経歴にこだわる心を棄てて、念仏申す身となれば、この先何があろうと、必ず浄土に生まれ、仏と成る事を約束された人生を、共に生きて往ける、と信じられる世界が開けます。人生は未来によって決まる、という現在を賜るのが、浄土の証です。「必ず滅度(=生死の迷いを超越した悟りの境地)に至る」という、確かな未来を、疑い無く信じられると、すべての後悔、苦悩、不安が、御恩に変化します。
苦悩の過去が無かったら、浄土を願う身には成れなかった私です。つらかった過去も、現在の苦しみも、未来への不安も、すべてが、私を浄土に向かって歩ませる、無くてはならない動機だったのです。そのことに頷けば、後悔と苦悩と不安に満ちた私の生活が転ぜられ、精一杯努力せずにはおれない、報恩の生活が始まるから不思議です。
この法語は、わずかに13文字で、浄土真実の証を表しています。仏教用語を用いずに、聞く者が、深く思いを回らし、なるほどと、頷き、過去の束縛から解放され、明るい未来に向かって歩み始める現在を賜る、深い不思議な言葉です。
「信に死し 願に生きよ」と示された曽我量深先生の言葉と同様に、聞く者が、永遠の未来に向かって歩み出す、力を賜る言葉です。
藤代先生は、明治44年福岡県田川郡糸田町の伯林寺の生まれで、日中戦争からの帰還後、お寺を弟様に託し、京都に移住されました。曽我量深先生がGHQから公職追放処分を受けられると、大谷大学の職を辞し、曽我師の随行(ずいこう=目上の人のともをし、つき従って行くこと。また、そのともの者)として、伝道の旅を続けられました。平成5年4月、旅先の江田島市明慶寺で、82歳で入寂(にゅうじゃく=僧侶が亡くなること)されました。
従軍体験の苦悩を縁として、寺を出て、住職を辞し、一生かけて曽我先生の教えを聞思し、選択の大宝海に帰して、念仏成仏された藤代先生の遺教が、この法語です。
樋口 不可思(ひぐち ふかし)
1951年生まれ。九州教区八女組淨圓寺住職。
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
◎あけましておめでとうございます。旧年中は何かとお世話になりありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今年度の法語カレンダーのテーマは、昨年に続き「宗祖親鸞聖人に遇う」です。親鸞聖人のみ教えにふれた先達のお言葉を通して、あらためて宗祖に出遇っていただきたいと願い、13点の法語を選定されたとのことです。(カレンダー裏面参照)
一年間ともに味合わせていただきましょう。
合掌
2025年12月の法話
|
[12月の法語] |
|
確かなものは 今もはたらいている 如来の本願力 |
|
For certain, the power of the Tathagata's Primal Vow is working right now. |
|
村上 速水 |
[法話]
外国の観光客に人気がある飛騨高山(ひだたかやま:岐阜県北部の高山市)の町並みを散歩していると、地図を持った外国人から道を尋ねられることがあります。
私は一緒に地図を覗き込み、流暢な外国語で、二つのことをお伝えしました。
「イマ、ココ!! ムキ、コッチ!! オーケイ??」
相手はとたんに笑顔になり、「サンキュー!!」と言いながら目的地へと向かっていきました。「迷う」というのは「現在地と方向がわからなくなる」ということなのですね。
でも、それは他人事ではありません。迷いの中にある私自身の人生を支(ささ)え、寄り添い続けてくださる確かなはたらきこそが、南無阿弥陀仏と仕上がった如来の本願力なのです。
40代後半自称「働き盛り」の私は、自分のキャパシティ(=人が受け止められる仕事量や、システムが処理できる能力の限界)以上に増えていくさまざまなお仕事にストレスを感じながらも、忙しい日々を充実して過ごしていました。
そこで起こった突然の交通事故と入院生活により、自分が抱えていたものが全て私の手から「もぎ取られて」いったのです。それだけではなく、少しでも打ちどころが悪かったら「このまま死ぬかもしれない」という状況の一歩手前までいきました。明日も、来年も、当たり前のように私の人生が続いていくという、私の勝手な思いがもぎ取られていったのです。
私の現在地が知らされるとはこういうことなのか。明日も来年もあって当たり前だと思っていた日々は、もう来ないかもしれない。そういういのちを生きているのが私なのだ、と。
だから「今、ここでの救い」なのです。明日や来年では間に合わないこの私に、阿弥陀さまの願いは、はたらきかけられているのです。
「あなたを救う仏に私が成る。かならず救う、われにまかせよ」
これまで多くのご門徒さんに、阿弥陀さまのお心をお伝えしてきたつもりでした。でもどこかで他人事だったのかもしれません。あの事故に遭って、私は本当に心の底から「我がこと」としてその願いを聞かせていただけたように思います。
「あらゆるいのちを救う仏に私が成る」との阿弥陀さまの願いが、この私のためであったと聞かせていただく。
これが、私にとっての「今、ここでの救い」でありました。
私が積み上げてきた知識や経験を「確かなもの」であると握りしめている生き方こそが、「迷い」そのものでありました。
迷いの中で私が握りしめていたものが全てもぎ取られていく中で、その私を根底から支え、寄り添い続けてくださっているのが、阿弥陀さまのご本願(=人々を救うために修行の際に立てた誓願)のはたらきでありました。
確かなものは、私が握りしめた知識や経験ではありませんでした。お念仏申す中で、今もはたらいている如来の本願力に支えられ、寄り添われている人生を歩んでいくのです。
朝戸 臣統(あさと たかつな)
本願寺派布教使、仏教婦人会総連盟講師、
布教使課程主任講師、岐阜県高山市神通寺住職
本願寺出版社(本願寺派)発行『心に響くことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註] 村上速水 : 1919~2000 日本の仏教学者。浄土真宗の僧
◎先月は当寺の報恩講法要へ多数ご参詣くださりありがとうございました。今回ご講師の大原観誠先生からは大阪の真宗寺院や当寺の歴史を私の知らない内容までお話しいただき大変勉強になりました。参詣の皆様方も興味深いお話に聞き入っておられました。さて今年もあと一月となりました。大阪・関西万博をはじめ様々な出来事があった一年でしたが皆様いかがお過ごしだったでしょうか。いいことも悪いこともすべて手を合わせ静かに受け入れ締めくくる年越しでありますようお念じ申し上げます。
南無阿弥陀佛。
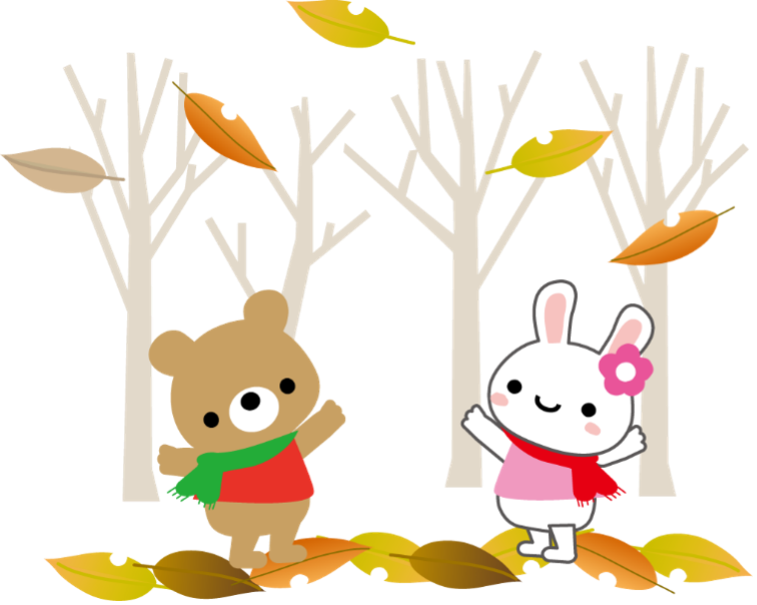
2025年11月の法話
|
[11月の法語] |
|
浄土へ生まれたい というのは 浄土へ生まれよ という 如来の命令なんだ |
|
Our wish to be born in the Pure Land arises from what the Tathagata tells us. |
|
仲野 良俊(なかのりょうしゅん) |
[法話]
「浄土へ生まれたい」
わたしたちは常日頃からそう思って生きているでしょうか? すぐに首を縦に振ることのできない問いだと思います。ここに「浄土へ生まれよ」という「如来の命令」の意義があるのでしょう。そもそも、人間というのははじめから「浄土」を求めているわけではありません。むしろ「浄土」すら知らないのです。または知っている気になっていて、実は知らないともいえます。
私は真宗寺院に生まれ、幼いころからお念仏の中で生活していたものの、大学生までの間ずっと背を向けて生きてきました。大谷大学へ行くことになった時も、最後の反抗で真宗学科には入学せず、歴史学科に入り教員を志していました。
しかし、転機が訪れます。きっかけは同じ境遇の友、そして恩師との出あいです。大谷大学は全国から寺院に生まれた人たちがたくさん集まります。二十歳そこそこの学生ですから、皆、表面的には反抗が見られるのですが、私と違って彼らの会話の中には真宗の話が端々に現れていました。正直、そこで初めて自分がお寺に生まれながら「浄土」を知らないことに気づかされました。もちろん、長年耳にしていた言葉ですから、初めて聞いたわけではありません。何度も、何度も触れていたはずなのに知らなかったのです。自分が恥ずかしくなりました。
ある時、「このままではダメだ」という気持ちに悩み、真宗学の勉強会に参加しました。そこでお世話になった先生のお話が忘れられず、のちに大学院へ入学し、私の真宗への学びは始まりました。最終的には六年という長い期間、大学院でお世話になることになります。
さて、私ははじめ真宗教義に学べば「浄土に生まれる」ということも理解できるだろうと思っていました。端的(たんてき=はっきりと)に言えば、大変浅はかながら「浄土に生まれたい」と思うようになれると考えていたの です。ところが、どれだけ学んでも、「浄土に生まれたい」という心が起こらない自分がはっきりするばかりでした。そこではっとしました。私は「浄土」の意味を勘違いしていたのだと。
私は「浄土」をこの現実から遠く離れた、どこか別の世界だと思っていました。目に見えないものですから、ある意味でこう考えるのは当然かもしれません。ただ、このように考えてしまうと、途端に「現在」とは無関係のものになってしまいます。ここが私にとって大きな問題だったのです。「だったら今は関係ないじゃないか」――何度もそう思った記憶があります。ですが、「浄土」とは現在を離れてあるものではないのです。
親鸞聖人は、真実に報いた世界を「浄土」と示し、その世界は如来の限りない光と限りない命の成就を根拠としている、と明らかにされています。言い換えるなら、如来のはたらきは時空を超えており、一切の限界がないということです。ですから、「浄土」とは、今現にわれわれ衆生に関わり、はたらき続けている如来そのものと決して別ではないのでしょう。だからこそ、私に「浄土へ生まれたい」という起こるはずのない心が発おこるのです。
あれだけ反抗していた私がいま自坊で法務をさせていただいている。如来のはたらきの中に生きる意味を考えずにはおれません。
岩田 香英(いわた こうえい)
1992年生まれ。名古屋教区第21組新福寺衆徒
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註]:仲野 良俊 1916~1988 浄土真宗僧侶(真宗大谷派)、仏教学者
◎先月半ば過ぎより長期間にわたる暑さも終わり秋も深まって参りました。最近は朝晩が肌寒く感じるほどですが皆さまいかがお過ごしでしょうか。
大阪関西万博も盛況の内に先月終幕しました。万博ロスという言葉をきくほど万博にはまって何度も足を運ぶ方がいるほど人気があったようです。私は残念ながら一度も行くことがかなわなかったのですがテレビ等で盛況ぶりを拝見することができました。開催前は何かと否定的なこともいわれていたので本当によかったと思います。
今月は報恩講です。親鸞聖人のご命日を縁として、そのご遺徳を偲び感謝し、ご恩に報いるためなお一層聞法させていただくご法縁です。静かに手を合わせお念仏申したいと思います。
合掌

2025年10月の法話
|
[10月の法語] |
|
塵が塵のままに照らされてひかり輝いている |
|
Dust, when it is illuminated, shines and sparkles just as it is. |
|
西元 宗助 |
[法話]
半世紀以上も昔のこと、原始仏教を学びたく関東から大谷大学へ入学。最初の高倉日曜講演のご講師が西元宗助先生でした。「自分とはどういう存在なのか。生きる意味はどこにあるのか」を暗中模索(あんちゅうもさく=くらやみの中で手さぐりして捜すこと。転じて、様子がはっきりせず、目的を達する方法が分からないまま、いろいろ探るように試みること)していた頃で、お話の内容は記憶がなく、ただここでやっと求めてきたことが充たされる、空しい放浪を終われるかもしれないという予感で涙が止めどなく溢れたことをいまだに鮮明に覚えています。
幸いにご縁に恵まれて先生のご自宅でお話を伺う機会も増え、ご講演、ご著書を通じて先生から受ける最も大きなことは自己への内省(ないせい=自分自身の心と向き合い、自分の考えや言動について省みること)の厳しさ、包み隠さぬ率直さでした。それが冷静な論理的思考から感情的とも思える激しい自己否定へ突入される流れに私はしばしば息を飲む思いでした。そしてそれは多く親鸞聖人の書かれたものをご自身に引き当てられて一層深められる態(てい=ようす)でした。大学に入って初めて親鸞聖人に触れた私には驚きの連続でした。
先生のお話は昔話ではなく、いつも只今の瑞々しいお気持ちでした。
先生は多くの善知識(ぜんちしき=仏教において、人々を正しく仏道に導く、徳のある友人や師のこと)に恵まれていらして、そういう方々との会話やエピソードを語って聞かせてくださりながら、実は先生ご自身が一番感動なさっていらっしゃいました。
先生にご紹介いただいて、あの時代のお念仏を申す人々にお目にかかる幸いにも恵まれました。それは私にとってお念仏に、あるいは親鸞聖人に別の角度から向き合う機会になりました。
先生は、旧満州からシベリアへ運ばれる貨車の中でこんなに真剣にお念仏を称(とな)えてきたのだから奇跡が起きてシベリアへ行かずに済むはずだと信じ、願っていらしたことを告白されたことがありまし た。
何も起きなかったとき「神も仏もないものか」という心境になられた。しかし様々な困難にあって苦しみ悩んだお陰で、お念仏は自分に都合のよいことを呼び寄せる手立てではなく、どんなに不都合な境地(きょうち=体や心が置かれている状態)に立たされてもそれを受容(じゅよう=受け入れて取り込むこと)できるよう支えてくださるのがお念仏というところに漸く立たせていただいた──私の耳に残る先生のご感懐(かんかい=物事に触れて心が動かされ、ある思いを抱くこと、またはしみじみと心に思うこと)です。
その道程で何度も繰り返しご自身の煩悩(ぼんのう)の深さに打ちひしがれ、まさにそこで慈光(じこう=阿弥陀如来が放つ慈悲の光)に出遭われてこられた先生のご生涯で「塵が塵のままに照らされてひかり輝く」は先生のお念仏の原点と思われます。
私の書棚にある榎本栄一氏の詩集『群生海』を開くと「西元先生に薦められて」と書き込みがあります。先生はこの詩集を絶賛されました。
「ぞうきんは 他のよごれを いっしょけんめい拭いて 自分はよごれにまみれている」(「ぞうきん」)という詩を最初に紹介されましたが、「うぬぼれは 木の上から ポタンと落ちた 落ちたうぬぼれは いつのまにか また 木の上に登っている」(「木の上」)を膝を叩いて共感される先生が浮かびます。そして「塵」の自覚もすぐ消えてしまう私がいます。
渡邊 愛子(わたなべ あいこ)
1946 年生まれ。仏典童話作家
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註]
「西元 宗助」:(1909~1990)鹿児島市出身1932年 京都大学文学部哲学科(教育学)卒業。 京都府立大学名誉教授、ペスタロッチ賞(昭和35年)
「榎本栄一」:(1903~1998)仏教詩人。兵庫県淡路島三原郡阿万町(現南あわじ市)生まれ。浄土真宗に帰依して念仏のうたと称する仏教詩を書く。1994年仏教伝道文化賞受賞。

2025年9月の法話
|
[9月の法語] |
|
大悲のなかに 大悲のなかに 確かにこの私がいます |
|
Embraced and surrounded by great compassion--this is where I surely am. |
|
外松 太恵子 |
[法話]
全国各地から京都の本願寺に門徒(もんと=浄土真宗の信者)さんが集まって、3泊4日の研修(門徒推進員中央教修)が行われます。
私もスタッフとして、何度かご一緒させていただきました。
少人数の車座(くるまざ=大ぜいが輪になってすわること)になって、互いに話し合い、聞き合い、頷(うなず)き合うという「話し合い法座」を重ねる中、少しずつ心の扉を開いて、ホンネを語ってくださいます。
お互いの思いを受け止め合ってくださる参加者のおかげでもありますが、その根底には、共に阿弥陀さまのお慈悲に願われ、支えられているのだという、み教えのはたらきがありました。
「私はここにいて良いのだ。ここでホンネをさらけ出すことを許されているのだ」という「本当の居場所」を与えられていると感じるのです。
振り返ってみると、私たちは幼い頃から頑張ることや努力することが大切だと教えられてきました。
時には、自分の主張を押し通したりライバルとの競争に打ち勝つことで、自分の思い通りの「居場所」を手に入れることが大切なのだと信じて、一生懸命に生きてこられたことでしょう。
また、自分の弱みを簡単に見せないように、周りから傷つけられないように、たくさんの鎧(よろい)を身にまといホンネを見せないようにして生きてきたのではないですか。
鎧を着込みホンネを隠して暮らしていく中で、知らず知らずのうちに不満とストレスを溜(た)め込みながら、「つらいなあ、しんどいなあ」とも言えずに過ごしてきたのが、私のありようでした。
上手(うま)くいっている時は自分の手柄(てがら)を誇(ほこ)り、上手くいかない時にはその原因を相手に押し付けて「こんなはずではなかったのに。どうしてこうなってしまったのだろう」と悩み苦しんでいるのが、私のありようだったのです。
自分で掴(つか)み取ろうとする「居場所」には常に不満とストレスがつきまとい、本当の安心を得ることはできなかったのでした。
阿弥陀さまは、「悲しみや苦しみを抱(かか)えたままのあなたを救う仏に、私が成る」
との願いを成就(じょうじゅ)され、南無阿弥陀仏の「名告(なの)りの仏」と成ってくださいました。
「あなたを決して一人ぼっちにはさせないよ。あなたの悲しみや苦しみをそっくりそのまま引き受けるよ。良い時のあなたも、悪い時のあなたも、背を向けはねつけている時のあなたも、追いかけ寄り添(そ)い続けるよ。だから、どうか私にまかせてくれよ。南無阿弥陀仏とお念仏申してくれよ」
阿弥陀さまの大悲に願われている私には、着込んだ鎧を脱ぎ、ありのままの私をさらけ出すことのできる「本当の居場所」が、確かに与えられているのです。
朝戸 臣統(あさと たかつな)
本願寺派布教使、仏教婦人会総連盟講師、
布教使課程主任講師、岐阜県高山市神通寺住職
本願寺出版社(本願寺派)発行『心に響くことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
◎9月になっても酷暑が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。夏の疲れも出てくる頃なのでくれぐれもご自愛くださいますようお念じ申し上げます。
さて今月は秋のお彼岸です。9月23日が秋分の日(彼岸の中日)となり、この日をはさんだ七日間(9月20日~26日)がお彼岸です。お墓参りとともにご先祖をご縁として仏法に耳を傾けましょう
合掌

2025年8月の法話
|
[8月の法語] |
|
仏様にあいたい これにまさる深い願いが人間にあるでしょうか |
|
Seeing the Buddha--is there any deeper wish that humans have? |
|
寺川 俊昭 |
[法話]
「みなさんは、仏さまになりたいと、ホンキで思っておられますか?」
ある研修会で、ドキッとするような問いをいただいたことがあります。
「そもそも仏さまがどういうお方かわからなければ、なりたいという気持ちも起こりようがありませんね。
仏さまというのは智慧(ちえ)と慈悲(じひ)を兼ね備えたお方、ということなんですよ。お慈悲のお心とは、自分のことを差し置いてでも、他者の幸せを願うことです。他者の幸せがそのまま自分の幸せとなるお方を、仏さまと申しあげるのです。
その仏さまに向き合うことで、私の中に智慧と慈悲のかけらもないことを知らされる。自分が幸せならばそれで良し、他人の幸せは妬(ねた)ましいとしか思えない私の姿が知らされる。そのようなお恥ずかしい私と知らされるからこそ、智慧と慈悲を兼ね備えた仏さまになりたいという、人生の方向性が確立されるのです。
なかでも阿弥陀如来という仏さまは、智慧と慈悲のかけらもない私を何としても仏に成らせたいという尊い願いを成就(じょうじゅ)されたお方です。すべての智慧と慈悲を自身のお名前として仕上げてくださり、南無阿弥陀仏とお念仏申すままが浄土に往(ゆ)き生まれて仏と成っていく道であるとお示しくださるのです」
私の中に智慧と慈悲のかけらもないと言われると「いやそんなことはない」と反発してしまいます。
大きな災害や、戦争・紛争のニュースを聞くたびに「かわいそうだな、何かしてあげたいな」という心を起こすこともあるのです。
でも、半日経(た)ったら「お腹すいたな、ご飯食べたいな」とさっきのことは忘れて、もう自分のことばかり考えている私です。私には末通(すえとお)った(=最後まで貫き通す)慈悲の心などありませんでした。
そんな仏さまと真逆の生き方をしている私は、多くの導きとお育てによってお念仏のみ教えに出遇(であ)わせていただきました。
私には人生を導いてくださった師が2人います。
「仏さまになりたい」などとかけらも思わなかった私を、仏前にいざない、仏法聴聞(ちょうもん)を進めてくださったお2人とも、先にお浄土に往かれました。お浄土からの導きとお育てをいただきながらお念仏申す中で、この私もかならず浄土に生まれて仏と成らせていただくことのありがたさを思います。
私も仏さまと成って、仏さまの世界でまたお目にかかりたい。この願いは私が自分の力で生み出したものではありませんでした。南無阿弥陀仏とお念仏申すままに、仏さまの世界から私を育て導いてくださっているのです。
この願いは、阿弥陀さまから賜(たまわ)った深く大きなお慈悲のはたらきによるものだといただけるのが、南無阿弥陀仏のお心でありました。
朝戸 臣統(あさと たかつな)
本願寺派布教使、仏教婦人会総連盟講師、
布教使課程主任講師、岐阜県高山市神通寺住職
本願寺出版社(本願寺派)発行『心に響くことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
◎今月はお盆です。お盆は正しくは「盂蘭盆(うらぼん)」といいます。浄土真宗では盂蘭盆会(うらぼんえ)のことを歓喜会(かんぎえ=よろこびのつどい)とも申します。故人のご縁によってお盆を迎え、尊いみ教えに出遇うことのできた身のしあわせを喜び、ご先祖に感謝のまことを捧げるのが、真宗門徒のお盆なのです。(真宗協和会「お盆のしおり」より抜粋)
連日大変な猛暑が続いています。熱中症が発生する約4割が住居内で最も多いです。こまめな水分補給とともにエアコンの適切な使用で室温、湿度を調整しましょう。
合掌

2025年7月の法話
|
[7月の法語] |
|
老いや病や死が人生を輝かせてくださる |
|
Aging, illness, and death enables life to shine. |
|
湯浅 成幸 |
[法話]
東雲(しののめ=東の空がわずかに明るくなる頃、あけがた)の空に生まれたばかりの太陽も、一日の終わりには西の彼方(かなた)へ沈(しず)んでゆくように、人もまたこの世に生を受けたならば、必ずその命を終えるときを迎(むか)えます。桃のような頬(ほお)のかわいらしい赤ちゃんも、やがて大人になるように、すべてのことは刻々と変化して移り変わっていきますが、同じ変化でも老いや病や死の現実は受け入れがたいものがあります。特に死を予感させるような病や生きていることに空(むな)しさを感じるような出来事に遭(あ)ったとき、「なぜ自分はこの世に生まれてきたのだろうか」「人生に意味などあるのだろうか」という問いが心の中に去来(きょらい)することでしょう。果たして私自身はこの問いにどのように向き合えるのだろうか。老病死の身を引き受けなければいけない事実は、人として生まれたからには誰一人避(さ)けられない問題です。
表題の「老いや病や死が、人生を輝かせてくださる」という言葉の前には「私たちにとっては、老いも病も死も、除(のぞ)かれるもの、不幸なことではなく、老病死によって生の豊かな営(いとな)みを教えられるわけです」という一文があります。「老いや病や死が、人生を輝かせてくださる」とはどういうことなのでしょうか。私はこの言葉を初めて聞いたとき、一昨年の秋に闘病中の母と交(か)わした言葉を思い出しました。
2022年の晩夏に体調を崩(くず)した母は、病院での検査の結果、投薬治療を行うことになりました。二回目の投薬のために入院する際、待合室で一緒に座っていたときのことです。当時はコロナ下にあり、家族は病室へ入ることができず、しばしの別れに不安と寂しさを感じていました。そのとき母は、「74歳になって、この年まで生きてこられて良かった。お父さんと結婚して、子どもも生まれて、孫にも会えて良かった。精いっぱいに生きてきたから悔(く)いはない」と、そして後に続く言葉は、生き死には阿弥陀さんにお任(まか)せして治療に向かうと語っているように聞こえました。
治療によってもし病が癒(い)えて体に力が戻ったら、母の願いはもう一度台所に立って料理をすることでした。ささやかな日常こそもう一度取り戻したいかけがえのない大切なものであることを教えられ、一緒に泣き笑いして過ごしたたくさんの時間が一瞬の出来事のように感じられました。親子として濃密に過ごした日々に生じた様々な感情も、母を看取(みと)るまでの間に解きほぐされ、母に「ありがとう」「ごめんね」と伝えると「こちらこそ」と返事をくれて、お互いにゆるし合う時間が持てたのもまた、かけがえのないことでした。
人間の眼からは、老病死や人生の挫折(ざせつ)は何としても避(さ)けたいことに思われます。しかし、人生を海に、仏の智慧や慈悲をお日さまと譬(たと)えるならば、命の終わる頃、黄昏時(たそがれどき=夕焼けで薄暗い中、景色が黄金色に輝く時間帯)の海は夕日に照らされ金色に輝き、その豊かさと美しさを知ることのできる大切な時間なのではないでしょうか。
別れは悲しい、けれども悲しいと同時にその人の存在と人生とは尊いものであることを知らされる大事な機会であるように思われます。
立島 直子(たつしま なおこ)
1975 年生まれ。富山教区第1組稱名寺衆徒
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註]湯浅 成幸:1930年熊本県生まれ。真宗大谷派山田寺前住職。
現在、熊本刑務所教誨(きょうかい)師。篤志(とくし)面接員
◎暑い日が続いています。先月後半には早くも梅雨明け宣言がなされました。年々暑い時期が長くなっているような気がします。くれぐれも熱中症には気をつけてお過ごし下さい。
合掌

2025年6月の法話
|
[6月の法語] |
|
何に遇ったのか それによって その人生は決定する |
|
Whatever you encounter in life will determine how your life will be. |
|
梯 實圓(かけはし じつえん) |
[法話]
「遇(あ)う」とは「ただ顔を合わせるだけではない」と梯實圓(かけはしじつえん)師は言われます。「遇」には「思いがけなく」という意味があります。わたしたちがどれだけ多くの人と出会い、言葉を交(か)わそうとも、自分の言いたいことを言い、聞きたいことを聞くのみであれば、自分の「思い」の中で他者と対面しているにすぎません。「思い」もよらなかった相手の心に触れ、「思い」に覆(おお)われていたわたし自身が知らされる時、「会う」は「遇う」になるのだと思います。
「遇う」ことは、ですから難しいことです。身近な家族であっても、たとえば本当に親が子に遇い、子が親に遇うということは、難しいことではないでしょうか。時には相手が亡くなり、初めて「遇う」ことが始まるということもあるでしょう。
会っていても遇えないのは、わたしたちが自分の「思い」を生きているからです。たとえるなら、お互いが、光でないものを光と思って歩んでいるようなものです。衝突(しょうとつ)するか、無視をしてやり過ごすか。そこに苦しみが生まれます。だからこそ、仏弟子たちは「仏に遇う」ことを課題に歩みました。流転(るてん=生まれ変わり死に変わって迷いの世界をさすらうこと)の苦しみを超えたお釈迦さまに、人生を照らし出す光を求めたのです。では、仏弟子たちはどのように仏と出遇ってきたのでしょうか。次のようなエピソードが伝えられています。
お釈迦さまの時代にヴァッカリという仏弟子がいました。お釈迦さまを篤(あつ)く敬(うやま)っていましたが、病にかかり、お釈迦さまに会いに行くことができなくなります。お釈迦さまはヴァッカリのもとへお見舞いに行かれます。ヴァッカリは「力が衰(おとろ)えてしまい、お釈迦さまのもとヘ伺(うかが)い、お姿を拝見することができなくなりました」と自らの悩みを打ち明けます。そのヴァッカリに対してお釈迦さまは次のようにおっしゃいます。「わたしのこの腐(くさ)りゆく身体を見て何になるのですか。法を見るものがわたしを見るのです」と。
たとえお釈迦さまと同じ時代に生まれ、お釈迦さまを見ることができても、仏陀 (目覚めた人)としてのお釈迦さまを見たことにはならないのです。お釈迦さまが目覚めたところの法(=仏法)を真(まこと)と受け入れること、それこそが仏陀を見ることであり、「仏に遇う」ことなのです。
仏弟子の集(つど)いである僧伽(そうぎゃ)では、お釈迦さまの言葉をたよりにその法が尋(たず)ねられ、仏陀との出遇いが深められていきました。その出遇いがもつ普遍性(ふへんせい=すべての物事に通じる性質)は、法蔵(ほうぞう)菩薩(阿弥陀仏)と世自在王仏(せじざいおうぶつ)の出遇いとして説き出されます。親鸞聖人は法然上人と出遇い、南無阿弥陀仏の教えこそが、お釈迦さまの本当に伝えたかった教えであり、お釈迦さまを仏陀たらしめた法であると頷(うなず)かれました。親鸞聖人は法然上人を通してお釈迦さまに出遇われ、その根底にある阿弥陀仏の本願に出遇われたのです。
その本願は「南無阿弥陀仏」という喚(よ)び声となってわたしたち一人ひとりに届いています。誰の人生においても「仏に遇う」道は開かれているのです。念仏申し、教えの光に照らされればこそ、身近な人と、また亡き人とも出遇っていけるのではないでしょうか。 「つらいこともあり、苦しいこともあり、嫌なこともあったけれども、仏陀に出遇えた私の人生に悔いはありません」。梯師は、わたしたちが「仏に遇う」ならば、このように言うことのできる人生が生きられていくと教えてくださいます。
千賀 貴信(ちが たかのぶ)
1979 年生まれ。大阪教区第20組西德寺住職
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註]:梯 實圓(1927~2014)日本の仏教学者。浄土真宗本願寺派勧学
◎先月は夏のように暑い日があるかと思えば肌寒い日があって不順な気候が続きました。皆様の体調はいかがでしょうか。
もう30年以上前ですが本山にて(今月の法語の)梯實圓先生のご講義を拝聴しました。柔らかな口調でわかりやすく浄土真宗の教えを学ぶことができました。優しいお人柄をお話の中に感じることができました。ご往生されて10年以上経ちますが今となっては懐かしい思い出です。
合掌