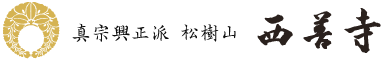2025年10月の法話
|
[10月の法語] |
|
塵が塵のままに照らされてひかり輝いている |
|
Dust, when it is illuminated, shines and sparkles just as it is. |
|
西元 宗助 |
[法話]
半世紀以上も昔のこと、原始仏教を学びたく関東から大谷大学へ入学。最初の高倉日曜講演のご講師が西元宗助先生でした。「自分とはどういう存在なのか。生きる意味はどこにあるのか」を暗中模索(あんちゅうもさく=くらやみの中で手さぐりして捜すこと。転じて、様子がはっきりせず、目的を達する方法が分からないまま、いろいろ探るように試みること)していた頃で、お話の内容は記憶がなく、ただここでやっと求めてきたことが充たされる、空しい放浪を終われるかもしれないという予感で涙が止めどなく溢れたことをいまだに鮮明に覚えています。
幸いにご縁に恵まれて先生のご自宅でお話を伺う機会も増え、ご講演、ご著書を通じて先生から受ける最も大きなことは自己への内省(ないせい=自分自身の心と向き合い、自分の考えや言動について省みること)の厳しさ、包み隠さぬ率直さでした。それが冷静な論理的思考から感情的とも思える激しい自己否定へ突入される流れに私はしばしば息を飲む思いでした。そしてそれは多く親鸞聖人の書かれたものをご自身に引き当てられて一層深められる態(てい=ようす)でした。大学に入って初めて親鸞聖人に触れた私には驚きの連続でした。
先生のお話は昔話ではなく、いつも只今の瑞々しいお気持ちでした。
先生は多くの善知識(ぜんちしき=仏教において、人々を正しく仏道に導く、徳のある友人や師のこと)に恵まれていらして、そういう方々との会話やエピソードを語って聞かせてくださりながら、実は先生ご自身が一番感動なさっていらっしゃいました。
先生にご紹介いただいて、あの時代のお念仏を申す人々にお目にかかる幸いにも恵まれました。それは私にとってお念仏に、あるいは親鸞聖人に別の角度から向き合う機会になりました。
先生は、旧満州からシベリアへ運ばれる貨車の中でこんなに真剣にお念仏を称(とな)えてきたのだから奇跡が起きてシベリアへ行かずに済むはずだと信じ、願っていらしたことを告白されたことがありまし た。
何も起きなかったとき「神も仏もないものか」という心境になられた。しかし様々な困難にあって苦しみ悩んだお陰で、お念仏は自分に都合のよいことを呼び寄せる手立てではなく、どんなに不都合な境地(きょうち=体や心が置かれている状態)に立たされてもそれを受容(じゅよう=受け入れて取り込むこと)できるよう支えてくださるのがお念仏というところに漸く立たせていただいた──私の耳に残る先生のご感懐(かんかい=物事に触れて心が動かされ、ある思いを抱くこと、またはしみじみと心に思うこと)です。
その道程で何度も繰り返しご自身の煩悩(ぼんのう)の深さに打ちひしがれ、まさにそこで慈光(じこう=阿弥陀如来が放つ慈悲の光)に出遭われてこられた先生のご生涯で「塵が塵のままに照らされてひかり輝く」は先生のお念仏の原点と思われます。
私の書棚にある榎本栄一氏の詩集『群生海』を開くと「西元先生に薦められて」と書き込みがあります。先生はこの詩集を絶賛されました。
「ぞうきんは 他のよごれを いっしょけんめい拭いて 自分はよごれにまみれている」(「ぞうきん」)という詩を最初に紹介されましたが、「うぬぼれは 木の上から ポタンと落ちた 落ちたうぬぼれは いつのまにか また 木の上に登っている」(「木の上」)を膝を叩いて共感される先生が浮かびます。そして「塵」の自覚もすぐ消えてしまう私がいます。
渡邊 愛子(わたなべ あいこ)
1946 年生まれ。仏典童話作家
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註]
「西元 宗助」:(1909~1990)鹿児島市出身1932年 京都大学文学部哲学科(教育学)卒業。 京都府立大学名誉教授、ペスタロッチ賞(昭和35年)
「榎本栄一」:(1903~1998)仏教詩人。兵庫県淡路島三原郡阿万町(現南あわじ市)生まれ。浄土真宗に帰依して念仏のうたと称する仏教詩を書く。1994年仏教伝道文化賞受賞。