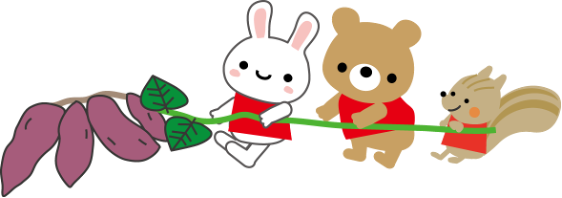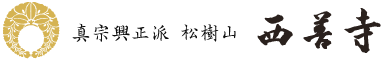2025年6月の法話
|
[6月の法語] |
|
何に遇ったのか それによって その人生は決定する |
|
Whatever you encounter in life will determine how your life will be. |
|
梯 實圓(かけはし じつえん) |
[法話]
「遇(あ)う」とは「ただ顔を合わせるだけではない」と梯實圓(かけはしじつえん)師は言われます。「遇」には「思いがけなく」という意味があります。わたしたちがどれだけ多くの人と出会い、言葉を交(か)わそうとも、自分の言いたいことを言い、聞きたいことを聞くのみであれば、自分の「思い」の中で他者と対面しているにすぎません。「思い」もよらなかった相手の心に触れ、「思い」に覆(おお)われていたわたし自身が知らされる時、「会う」は「遇う」になるのだと思います。
「遇う」ことは、ですから難しいことです。身近な家族であっても、たとえば本当に親が子に遇い、子が親に遇うということは、難しいことではないでしょうか。時には相手が亡くなり、初めて「遇う」ことが始まるということもあるでしょう。
会っていても遇えないのは、わたしたちが自分の「思い」を生きているからです。たとえるなら、お互いが、光でないものを光と思って歩んでいるようなものです。衝突(しょうとつ)するか、無視をしてやり過ごすか。そこに苦しみが生まれます。だからこそ、仏弟子たちは「仏に遇う」ことを課題に歩みました。流転(るてん=生まれ変わり死に変わって迷いの世界をさすらうこと)の苦しみを超えたお釈迦さまに、人生を照らし出す光を求めたのです。では、仏弟子たちはどのように仏と出遇ってきたのでしょうか。次のようなエピソードが伝えられています。
お釈迦さまの時代にヴァッカリという仏弟子がいました。お釈迦さまを篤(あつ)く敬(うやま)っていましたが、病にかかり、お釈迦さまに会いに行くことができなくなります。お釈迦さまはヴァッカリのもとへお見舞いに行かれます。ヴァッカリは「力が衰(おとろ)えてしまい、お釈迦さまのもとヘ伺(うかが)い、お姿を拝見することができなくなりました」と自らの悩みを打ち明けます。そのヴァッカリに対してお釈迦さまは次のようにおっしゃいます。「わたしのこの腐(くさ)りゆく身体を見て何になるのですか。法を見るものがわたしを見るのです」と。
たとえお釈迦さまと同じ時代に生まれ、お釈迦さまを見ることができても、仏陀 (目覚めた人)としてのお釈迦さまを見たことにはならないのです。お釈迦さまが目覚めたところの法(=仏法)を真(まこと)と受け入れること、それこそが仏陀を見ることであり、「仏に遇う」ことなのです。
仏弟子の集(つど)いである僧伽(そうぎゃ)では、お釈迦さまの言葉をたよりにその法が尋(たず)ねられ、仏陀との出遇いが深められていきました。その出遇いがもつ普遍性(ふへんせい=すべての物事に通じる性質)は、法蔵(ほうぞう)菩薩(阿弥陀仏)と世自在王仏(せじざいおうぶつ)の出遇いとして説き出されます。親鸞聖人は法然上人と出遇い、南無阿弥陀仏の教えこそが、お釈迦さまの本当に伝えたかった教えであり、お釈迦さまを仏陀たらしめた法であると頷(うなず)かれました。親鸞聖人は法然上人を通してお釈迦さまに出遇われ、その根底にある阿弥陀仏の本願に出遇われたのです。
その本願は「南無阿弥陀仏」という喚(よ)び声となってわたしたち一人ひとりに届いています。誰の人生においても「仏に遇う」道は開かれているのです。念仏申し、教えの光に照らされればこそ、身近な人と、また亡き人とも出遇っていけるのではないでしょうか。 「つらいこともあり、苦しいこともあり、嫌なこともあったけれども、仏陀に出遇えた私の人生に悔いはありません」。梯師は、わたしたちが「仏に遇う」ならば、このように言うことのできる人生が生きられていくと教えてくださいます。
千賀 貴信(ちが たかのぶ)
1979 年生まれ。大阪教区第20組西德寺住職
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註]:梯 實圓(1927~2014)日本の仏教学者。浄土真宗本願寺派勧学
◎先月は夏のように暑い日があるかと思えば肌寒い日があって不順な気候が続きました。皆様の体調はいかがでしょうか。
もう30年以上前ですが本山にて(今月の法語の)梯實圓先生のご講義を拝聴しました。柔らかな口調でわかりやすく浄土真宗の教えを学ぶことができました。優しいお人柄をお話の中に感じることができました。ご往生されて10年以上経ちますが今となっては懐かしい思い出です。
合掌

2025年5月の法話
|
[5月の法語] |
|
仏さまというのは向こうから私のところへいつも来ているはたらきです |
|
"Buddha" is the dynamic working that comes to me constantly. |
|
近田 昭夫 |
[法話]
親鸞聖人は、当時の僧侶の常識を破り、結婚して家庭を持たれました。
妻の恵信尼(えしんに)さまのお手紙や、曾孫(ひいまご)の覚如(かくにょ)上人の伝記によれば、29歳の時に比叡山を下り、六角堂に100日間参籠(さんろう=祈願のため、神社や寺院などに、ある期間こもること。おこもり。)された中、95日目の明け方、夢の中に観音菩薩が現れて、こうお告げをされたのです。
「もしあなたが女性と結婚するのであれば、私がその相手となりましょう。そして一生あなたと添(そ)い遂(と)げたあと、いのち終わる時にはかならずお浄土に生まれる身といたしましょう」
つまり、親鸞聖人にとって結婚相手の恵信尼さまは、観音菩薩の化身(けしん=世の人を救うために人の姿となって姿を現した仏)であったわけです。結婚するということは、パートナーと共にお念仏申す人生を歩むということなのです。そしていのち終わる時には、お浄土に往生する身と成らせていただくのです。
妻の恵信尼さまもお手紙の中で、夫としての親鸞聖人を「観音菩薩の化身」であったとお書きくださっています。
観音菩薩とは、阿弥陀さまの脇侍(わきじ)(左脇に侍する菩薩、脇士とも)であり、大慈悲のはたらきを備えておられます。お経には、苦しむいのちを救うために、老若男女さまざまなお姿になって娑婆(しゃば=煩悩 (ぼんのう) や苦しみの多いこの世。現世)世界に現れてくださるのだと説かれてあります。
人生のパートナーが、お互いを観音菩薩の化身であるということは、私を仏道に導いてくださるお方が、すでに私の目の前におられるということです。お互いを敬い、共に手を合わせ、お念仏申していけるとは、なんて素敵な人生なのでしょう!
親鸞聖人と恵信尼さまは、お互いのいのちの中にご自身をお育てくださる仏さまのはたらきを見ていかれ、菩薩さまの化身と仰(あお)がれたのです。
ただ、どんなに仲の良いパートナーであっても、時にはケンカや仲違(なかたが)いをするかもしれません。どんなに傍(かたわら)に寄り添っている者同士でも、さまざまな理由で離れ離れで暮らさないといけないこともあるかもしれません。
そんなパートナーの存在を「私を仏道に導いてくださる方」と手を合わせていけるのが、お念仏の人生なのです。
そして親鸞聖人は90歳で、恵信尼さまより先にご往生なさいました。「今度は、仏さまの世界から私を導き、寄り添ってくださるはたらきと成られたのだ」と、恵信尼さまは手を合わせお念仏されたのではないでしょうか。
私から離れた、どこか遠いところに仏さまがおられるのではありません。仏さまは、縁あるお方のお姿となって、私を仏道へ導き、お育てくださいます。ありがたいお育てもあれば、厳しいご催促(さいそく)もあるでしょう。そのはたらきは、お念仏申す中で常に私のそばに寄り添い、すでに私のところへ来てくださっているのです。
朝戸 臣統(あさと たかつな)
本願寺派布教使、仏教婦人会総連盟講師、布教使課程主任講師、岐阜県高山市神通寺住職
本願寺出版社(本願寺派)発行『心に響くことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
◎ようやく春らしい季節となりあちらこちらで新緑が目立つようになりました。
先月、関西大阪万博が開催されました。いまだに完成されていないパビリオンがあるなど波乱含みのスタートとなりましたが連日にぎわっているようです。55年前の万博(EXPO70)開催時、私は小学3年生でした。家族と2回、学校の遠足で1回行きましたが、太陽の塔に入れたこと、延々と続く行列にうんざりしたこと、パビリオンごとに押してもらえるスタンプを集めたこと等々、今となっては懐かしい思い出です。今回の万博も一度は行ってみたいのですがどうなるかわかりません。55年前とはいろんなことがすっかり変わってしまいましたが、行ってみたら変わらないものがあることに気づくかもしれません。皆さんも探してみませんか。
合掌

2025年4月の法話
|
[4月の法語] |
|
この私のいのちにいつも如来のいのちが通い続けている |
|
The life of the Tathagata is a part of my life always. |
|
藤澤 量正 |
[法話]
「人生には、三つの『坂』があると申します。一つ目は上り坂、二つ目は下り坂。そして三つ目は『まさか』です」
結婚披露宴(ひろうえん)のスピーチで聞いたことのある「人生訓」ではありますが、私は40代半ばにしてその「まさか」に見舞われてしまいました。
当時の私は、住職として法務をこなし、父親として3人の子どもを育て、大きな大会の実行委員長を引き受けるという「充実した人生」を過ごしていました。
ところが突然、趣味の自転車で大きな交通事故に遭い、病院の集中治療室に担ぎ込まれてしまったのです。病室でモニターに囲まれながら、1週間後の大きな大会も、順風満帆な日常も、握りしめていた私の手から容赦なくもぎ取られていくことを実感していました。
同時に、今までご法話で話していたご法義(=仏法の教義、教え)のお心が本当に「わがこと」として深く味わわれたのです。
「かならず救う、われにまかせよ」
阿弥陀さまの願いは、この私をお救いくださるためでありました。
仕事も、健康も、そしていのちさえも、当たり前だと思い込み自分のモノであると掴(つか)んでいた私。でも私が掴んでいたものは、何一つ当たり前ではなく、末通(すえとお)った(=最後までやりとげる、最後までつらぬき通す、成功する)ものがありませんでした。
ひとたび縁に触れれば、どんなに私が掴もうとしても私の手からもぎ取られてしまう。それが、私のありのままであったのです。
でも「まさか、こんなはずでは」というのは私の視点、私の考えであって、阿弥陀さまは、そのような私であることをすでに見通しておられました。
「あなたを救う仏に、私が成る。あなたのいのちのすべてを、私が引き受ける」
と、阿弥陀さまが願いを起こされ、そのはたらきを「南無阿弥陀仏」というお念仏に仕上げてくださったのです。
病室でお念仏申しながら、不安を抱えた私をそのまま包みこんでくださる阿弥陀さまのお心を、しみじみと味わっていました。
私が人生に行き詰まる前から、仕事や健康をもぎ取られるずっと前から、阿弥陀さまのお慈悲のぬくもりは、ずっと私に届けられていました。
私がお願いしたから救いましょう、おすがりしたから助けましょう、と仰せになるのではありません。それだったらもう私には間に合いませんから、私は救いから漏れてしまうことになります。
私がお願いするより先に、気付くよりもずっと以前に、阿弥陀さまの方から私に寄り添い、お慈悲のぬくもりが届けられていたのです。
この私のいのちに、阿弥陀さまのいのちがすでに通い続け、届いていました。南無阿弥陀仏とお念仏申すなかで、そのありがたさをしみじみと感じます。
朝戸 臣統(あさと たかつな)
本願寺派布教使、仏教婦人会総連盟講師、布教使課程主任講師、岐阜県高山市神通寺住職
本願寺出版社(本願寺派)発行『心に響くことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註]藤澤量正 : 1923(大正12)年滋賀県に生まれる。龍谷大学文学部(仏教学専攻)卒業。鉄道道友会講師、伝道院研修部長、中央仏教学院講師を歴任。本願寺派布教使、滋賀県浄光寺前住職。2012(平成24)年7月往生。
◎全国各地で桜の開花情報が伝えられています。3月は初夏のように暖かくなったと思えば真冬のような寒さになったりと不順な気候でした。また2月末に岩手県大船渡市で発生し3月半ばになってようやく鎮圧した大規模な山林火災、3月末にはミャンマー中部で大地震の発生等々、災害の多さに気持ちがついて行けませんでした。被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。今月のご法話はだれにでも「まさか」の事態が起こりえること、そしてそれが実はありのままの人生であること、そんな私に気づかせてくださるのが阿弥陀さま(南無阿弥陀佛のお念仏)なのだと教えていただけました。
合掌
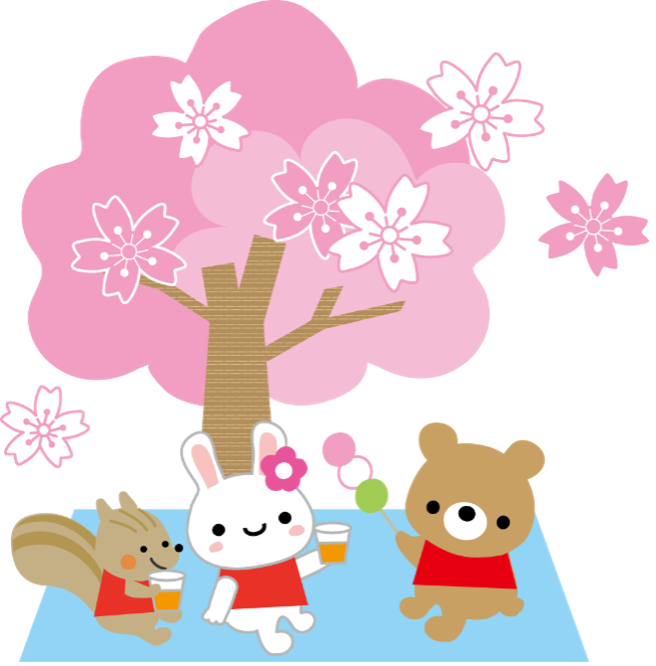
2025年3月の法話
|
[3月の法語] |
|
真の智慧はそのまま大悲でもある |
|
True wisdom is itself Great Compassion. |
|
上山 大峻(うえやまだいしゅん) |
[法話]
上山大峻氏の言葉に、ある人のことが思い浮かびます。
ある問題で悩んでいたとき、訪ねた人のことです。駅に迎えに来てくれたその人の車に乗せてもらうなり、私は話しはじめていました。だいぶ経(た)ってから名前を聞かれ、そこではじめて、ほぼ初対面であることに気づきました。
いま思うと、私の様子は異様であったかもしれません。言葉が止まりませんでした。ですが、その人は私の言葉をじっと聞いてくださいました。当時の私は「何もわからんくせに」「だまっとれ」「何を言うか」などの言葉を直接間接にたくさん投げかけられていましたから、私の言葉を否定せずに聞いてくださる人がいることに本当に驚きました。
親鸞聖人が大事にされた『観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)』に登場する韋提希夫人(いだいけぶにん)は、息子である阿闍世(あじゃせ)に牢獄(ろうごく)に幽閉(ゆうへい)され、釈尊(しゃくそん=釈迦の尊称)に対して「我、昔何の罪ありてか、この悪子を生ずる」(私に何の罪があって、このような子を生んだのか)と苦悩を打ち明けます。このことはしばしば「釈尊の前で愚痴(ぐち)をさらけだした」と解釈されてきました。しかし私はそう思えません。韋提希はそれまで誰にも話を聞かれていなかったのではないでしょうか。
「この人は私の話を聞いてくれるかもしれない」と思えてはじめて、言葉を語ることができたという経験をした人は少なくないはずです。釈尊との対峙(たいじ) を通して、韋提希は自分の声が誰からも聞かれてこなかったこと、そして自分もまた自身の声を軽視してきたことに気づいたのでしょう。そして韋提希が率直に自身の置かれている現実を語ったことによって、釈尊も「黙然(もくねん)として」(『観経疏』)その訴(うった)えを聞くことになったのだと思います。
韋提希は自分だけではなく、さらに未来を生きる他者も阿弥陀仏の教えに出遇(であ)えるようにと願うに至りますが、それも自分の言葉を無視しなかった釈尊の存在あってのことだったと思うのです。
これまで多くの女性が自分の言葉を「愚痴」と名づけるのを耳にしてきました。「愚痴ばっかりね」「愚痴聞いてもらっちゃった」というふうに。何気ないことですが、彼女たちはなぜ「愚痴」という言葉を用いたのでしょう。仏教における愚痴とは、根本的な無知を指す言葉です。韋提希の言葉がこれまで「愚痴」と捉(とら)えられてきたように、彼女たちにも「愚痴」と名づけられ続け、生まれたそばか ら軽んじられる苦悩が無数にあったのだと思います。
冒頭のある人は「私の身を案じてくれる門徒さんにたすけてもらってきたの」と言われました。私もいま、女性が抱(かか)える苦悩を「愚痴」と決めつけない、互いに話を聞き合える人たちをたよって、たすけてもらっています。
韋提希の物語は、王舎城(おうしゃじょう)という古代インドの王宮で一人の王妃に起きたことが説かれたものですが、同時に韋提希という一人の女性の現実を目の当たりにし、安直に「愚痴」と決めつけない釈尊の物語でもあります。つまり釈尊は韋提希の率直に自らを語る姿にはじめて、凡夫の現実の身にこそはたらく大悲のはたらきを見、このことを教えとして説いたのでしょう。上山氏の法語を通して、私はそのことにあらためて思いを致しています。
西寺 浄帆(さいじ しずほ)
1980 年生まれ。三重教区南勢1組本覺寺坊守
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
◎寒かった時期も過ぎてようやく春らしい季節になってきました。境内の梅(小さい木ですが)も少しずつつぼみが開き始めました。
今回の法語の上山大峻先生(1934~2022 元龍谷大学学長)は私の父(前住職)の古い友人で、私も大学で先生の授業を受けました。穏やかな風貌(ふうぼう)そのままの語り口で楽しく勉強させていただきました。授業中余談でされた示唆のあるお話は40年以上前のことですが今でも覚えており大変懐かしく思い起こされます。今回の言葉もしっかり心に刻みたいと思います。
合掌
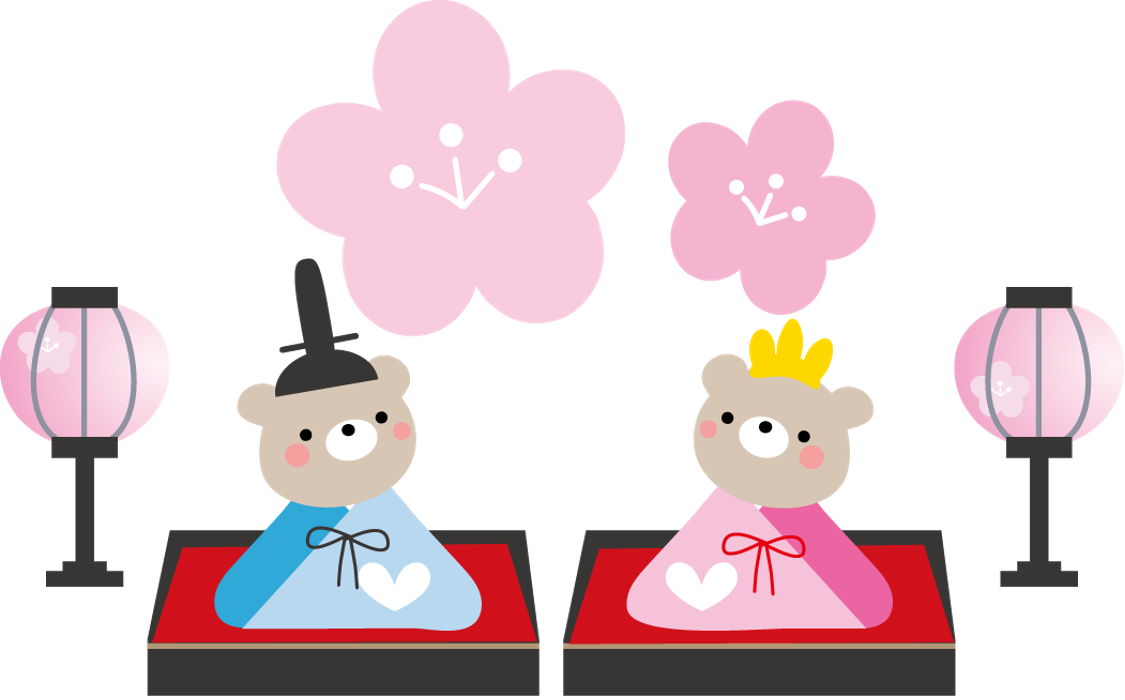
2025年2月の法話
|
[2月の法語] |
|
「名号」は私たちの地獄に響く阿弥陀のいのち |
|
The Name, Namu Amida Butsu, is the working of Amida that reverberates in the hell of my own delusion. |
|
高 史明(コ・サミョン) |
[法話]
この法語は、高史明先生のおことばです。一読して、広さと明晰(めいせき)さと確かさを感じます。それはこのおことばの中に、私とは何か、私を救うものは何か、どのように私を救うのかという、人間の救いの根本となる真実が説かれているからではないかと思われます。
私とは何か。「私たちの地獄に響く」とありますように、私という存在の一番奥深いところにあるものが「地獄」と言われています。
源信(げんしん 942~1017平安時代中期の天台宗の僧、浄土真宗七高僧の一人)の『往生要集(おうじょうようしゅう)』に八大地獄が説かれています。敵意をいだいて傷つけ合う等活(とうかつ)地獄。焼けた斧(おの)で刻(きざ)まれる黒縄(こくじょう)地獄などが克明(こくめい)に説かれ、八番目がいちばん底の阿鼻(あび)地獄。その苦しみは第一から七までの苦しみを合わせた千倍もあるのだと。
何を表しているのでしょうか。阿鼻地獄の苦しみは、賜(たまわ)ったご恩を忘れて生きる「五逆(ごぎゃく)」や、仏の大慈悲に背(そむ)き謗(そし)る「謗法(ぼうほう)」の者が受ける苦しみだと言われます。
仏様は私たちを「五逆謗法」の者だと明かされました。これを生み出しているのが無明(むみょう)煩悩(ぼんのう)です。高史明先生は、このおことばの出拠(でどころ)である『悲の海は深く』(東本願寺出版)の中で、仏を忘れ煩悩で自己中心的に生きることの誤りを、深い悲しみと熱い願いの中で指摘されています。
この私たちを救おうと立ち上がられたのが仏様なのです。「阿弥陀のいのち」と表されています。無 量無辺(むりょうむへん=限りないほど広々としていること)の真実です。その真実は動かない真実ではなく、迷い苦しむ私たちに向けて動き出します。そして私たちにはたらきかけ、救いを成立させるのです。
私は仏教に疑問を持っていましたが、学生時代に偶々(たまたま)の因縁で真宗の教えを聞くようになりました。お聞きしてよかったとつくづく思ったことは、阿弥陀は動かないものではなく、自ら私のために立ち上がり、歩み、はたらきかけてくださっていることをお聞きしたことです。自己中心的に生きる者としては考えられないことです。このことを知って仏教に対する私の気持ちはがらりと変わりました。
阿弥陀は南無阿弥陀仏という名号となって私を喚(よ)ぶ。私のほうから仏に向けて「お願いします」ではなく、阿弥陀のほうが、これがあなたを救う私(阿弥陀)という真実のすべてなのだよ。それ「南無阿弥陀仏」で表しているのだよと喚(よ)びかけてくださるのです。
地獄について親鸞聖人が説かれる教えの一つに阿闍世王(あじゃせおう)の物語があります。阿闍世は父を殺してこれを正当化しますが、罪を自覚し始め苦しみます。大臣から釈尊の教えを聞くことを勧められ、途中乗って行く象から落ちそうになり、落ちれば地獄に堕(お)ちるのではと恐れます。
その阿闍世が釈尊に会い、丁寧(ていねい)な教えを聞いて信心を得た時、地獄を恐れるどころか、国王として迷惑をかけた国民を救うためには阿鼻地獄の中におかれてもかまわない旨(むね)を釈尊に申し上げるのです。
南無阿弥陀仏は私たちの地獄に向けてはたらき、地獄を転回軸にして新たな真のいのちを生み出してくださるのです。
岡本 英夫(おかもと ひでお)
1947年生まれ。京都教区石東組德泉寺住職
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註]「名号」:仏・菩薩の名、ここでは南無阿弥陀仏の六字のこと。
◎年が明けてもう一月が経ちました。先月は少し暖かい日が続くこともありましたがまた寒さが戻ってきたように感じます。暦の上では春になりますがまだまだ寒さが続きそうです。何卒ご自愛くださいますようお念じ申し上げます。
合掌

2025年1月の法話
|
[1月の法語] |
|
いつでもどこでも 誰でも助ける行 それは念仏 |
|
The practice that enables anyone, at anytime, anywhere, to become liberated is none other than the Nembutsu. |
|
竹中 智秀(たけなかちしゅう) |
[法話]
私は10年以上前に、趣味の自転車で交通事故に遭(あ)い、大ケガを負って2カ月の入院生活を余儀(よぎ)なくされたことがあります。
その時にお世話になった救急医療のありようを通して、お念仏に込められた阿弥陀さまのお慈悲を思うきっかけとなりました。
中国の高僧 善導(ぜんどう)大師は、阿弥陀さまの大いなるお慈悲のありようについて、
「陸の上の人よりも、水の中で溺(おぼ)れている人を、急いでお救いくださる」という「救急の大悲」をお示しくださいました。
「苦しんでいるいのちを、なんとかして救いたい」という救急医療のありようを通して、阿弥陀さまのお心の一端(いったん)を思います。
「いつでも」・・・「夕方6時で受付を終わりますね、年末年始は休業しますね」という救急医療はあまり聞いたことがありませんね。24時間365日休むことなく、苦しむいのちを救いたい、という願いが救急医療に込められています。
「どこでも」・・・都会はいいけど、私が住んでいる飛騨(ひだ)の田舎はちょっとやめときますね、という救急医療も聞いたことがありませんね。どのような場所であっても、病気やケガで大変な目に遭っている人を救いたい、という願いが救急医療に込められています。
「だれでも」・・・救急医療の現場で「あなたちゃんと税金を納めていますか?」「支持する政党はどこですか?」とは聞かれませんね。治療を受ける患者さんに一切の区別・選別・差別をせず、あらゆる人を救いたい、という願いが救急医療には込められています。
ただし実際に救急病棟(びょうとう)に運ばれますと、腰を痛めた年輩の方や、熱を出して泣き止まない赤ちゃんより先に、私がまっさきに治療を受けることができました。
それはなぜなのか。救急医療の現場においては、最も大きなケガや病気を負った患者が、真っ先に治療を受けるべき「おめあて」である、ということなのです。
南無阿弥陀仏のお念仏に込められた阿弥陀さまのお慈悲とは、まさに「救急の大悲」でありました。
「いつであっても、どこであっても、あらゆるいのちを救う仏に、私が成る」との願いが完成され、南無阿弥陀仏のお念仏と成って、私が称(とな)えるまま、聞こえるまま、私の中に入り満ちてくださっています。
そのお心をよくよく味わっていきますと「今、ここで、この私が一番のめあて」と願われていました。最も大きな苦悩を抱(かか)え、最も救われ難いいのちであるこの私こそが、阿弥陀さまのお慈悲のど真ん中に包まれていたのです。
朝戸 臣統(あさと たかつな)
本願寺派布教使、仏教婦人会総連盟講師、
布教使課程主任講師、岐阜県高山市神通寺住職
本願寺出版社(本願寺派)発行『心に響くことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
◎今回は阿弥陀如来の働きを救急医療のありように例えながらのご法話でした。
ここで私が感じたのは、朝戸先生が大けがをして二ヶ月もの入院生活があればこそのお話でありお気づきであるということです。大過のない日常生活をしていて阿弥陀如来のお救いに気づくことは滅多にありません。気づいたと思ってもすぐに忘れてしまうのがこの「私」です。そんな「私」こそが救いの目当てであると仰せになるのが阿弥陀如来なのです。よくよく考えてみなければと改めて思いました。
合掌
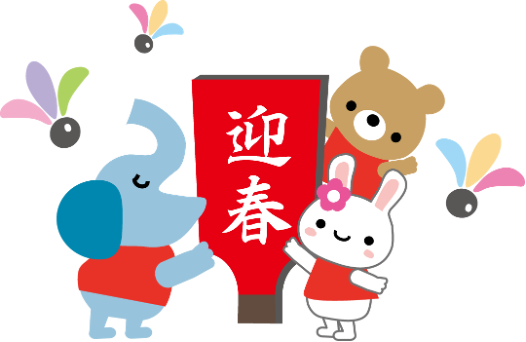
今年の法話(2025年)
|
[今年の法語] |
|
宗教とは生死を貫くまこと一つの教え |
|
Religion surely is a guide for one to cope with living and dying. |
|
中西 智海(なかにしちかい) |
[法話]
「死んだらおしまいですよね。生きているうちが花ですね」 ご法事の際に、参加者から聞こえてきた「ホンネ」です。 世の中では「よりよく生きる」ことがもてはやされ、死を遠ざけ、目を背(そむ)けていることが多いようです。でも、死を見つめなければ、本当の生もわからないのだと教えてくれるのが、宗教ではないでしょうか。
「蟪蛄は春秋を識(し)らず」とは、中国の思想家 荘子(そうし)が残した言葉だそうです。夏の暑い季節に地中から這(は)い出て成虫となるセミ(蟪蛄)は、春と秋を知ることはない、と仰(おお)せになりました。それを受けた中国の高僧 曇鸞(どんらん)大師は「この虫あに朱陽の節を知らんや」(『註釈版聖典七祖篇』98頁)と続けられたのです。つまり、春と秋を知らないセミは、夏(朱陽)が夏であることさえも知らないのだ、という譬(たと)えです。
曇鸞大師は、セミをバカにしているのではありません。私の姿を言い当てておられるのです。私のいのちがどこから来て(春)、どこへ行くのか(秋)を知らないままに人生を過ごすのであれば、人生の意味(朱陽)を知らないままに、虚(むな)しい人生となってしまうとおっしゃるのです。
私の日常では、生きていることが当たり前で、死は不幸にも突然にやってくるのだと思い込んでいます
「生は当然、死は突然」
というのが、私の握りしめた「モノサシ」です。
しかし、仏法に照らされることで、そうではない「モノサシ」が示されるのです。不思議なご縁が重なり合い、人として誕生することができた私であると同時に、この世の縁が尽きたならば、いのち終えていくことは必然なのでありましょう。
「生は偶然、死は必然」(金子大榮(かねこだいえい)師)
という、私のいのちのありようを、仏法は教えてくださいます。まさに「生死一如(しょうじいちにょ)」であり、生も死も分け隔(へだ)てできず、どちらも私のいのちの現実であることを知らされるのです。
残念ながら、私たち人間の限定的な知識の積み重ねでは、このいのちの行き先はわかりません。だからこそ、釈尊(しゃくそん=釈迦)が説かれた仏法を聴き、人知を超えた救いのはたらきを聴かせていただくのです。
自ら迷いを断ち切って、生死を超える道を歩みなさい、という仏道もありますが、親鸞聖人がお示しくださった他力念仏は、私に迷いを断ち切りなさい、自分で生死を乗り越えなさいという仏道ではありません。
苦悩と迷いを抱(かか)えて生きる私に「かならず救う、われにまかせよ」との願いを「南無阿弥陀仏」に仕上げてくださいました。
称(とな)えるまま、聞こえるまま、ずっと私に寄り添い続け、この世の縁が尽きる時には、かならず浄土に生まれて、仏と成らせていただく。
生死を貫くまことの教えは、南無阿弥陀仏と仕上がって、すでに阿弥陀さまから届いているのです
朝戸 臣統(あさと たかつな)
本願寺派布教使、仏教婦人会総連盟講師、
布教使課程主任講師、岐阜県高山市神通寺住職
本願寺出版社(本願寺派)発行『心に響くことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
◎あけましておめでとうございます。旧年中は何かとお世話になりありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
昨年は元日に能登半島地震があり大変でしたが今年は穏やかな年始を迎えることができました。このまま平和な日々が続いてくれたらと願うばかりなのですが、諸行無常(あらゆるものは例外なく移り変わってゆく)であり、山あり谷ありなのが人生です。だからこそこんな私たちを知恵と慈悲の光で照らしてくださる阿弥陀如来に全てお任せしこの一年も力強く生き抜いてゆきたいと思うのです。
合掌
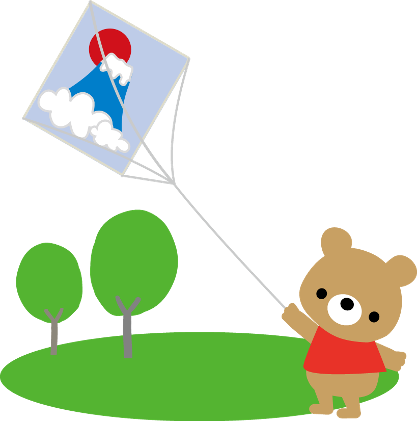
2024年12月の法話
|
[12月の法語] |
|
貴方の感じられている 虚しさこそ 真実の世界への 強烈な憧れなのです |
|
That empty feeling inside is just our heart yearning for that truly real world: the Pure Land. |
|
米沢英雄 |
[法話]
この法語は、『同朋』(東本願寺出版)1967年9月号の中で、米沢師が「若き友へ」と題した寄稿文(きこうぶん=依頼されて、新聞や雑誌などに送る原稿)に出てきます。若き青年が一流会社へ就職し三年が経ち、「この頃毎日、空虚(くうきょ=実質的な内容や価値がないこと。むなしいこと。また、そのさま)を感じている」というお手紙に対して返信された中での言葉です。
1967(昭和42)年は、日本の高度経済成長期の真っ盛りでありましょうか。その頃、この青年は今の今まで努力を惜しまずに頑張ってきたに違いありません。しかし、頑張っても頑張っても落ち着くところがない。次から次へと課題が押し寄せ、心から安心できる場所が見えない中で空虚さを感じずにおれなかったのです。それは世間の価値観に翻弄(ほんろう)され、もがき生きようとする中に、芽生(めば)えだした世間や自分自身に対する違和感でもあったことでしょう。そのような状況で、「今こそ方向転換のチャンスだ」と見たのがこのお言葉なのだと思います。
私たちは、どのような職業に就(つ)くにしても、この身を持ってこの世を生きる時、自分の能力が試される場を頂くことになります。私は、22年前、全く知らぬ地で入寺(現在の寺)しました。お寺には様々な行事がありましたが、その中に、入寺する前には聞かされていなかった日曜学校もありました。義母から、「貴方ならできるでしょう。さあどうぞ」といきなり手渡されたのです。
義母である「女先生」の後任として突然現れた私に、子どもたちは戸惑いもあったのでしょう。「デシ」というあだ名を付けられました。女先生の後任で、子どもたちよりも日曜学校の後輩であるがゆえ〝弟子〟にはちがいありません。それからというもの、道すがら子どもたちに遭遇(そうぐう=不意に出あうこと。偶然にめぐりあうこと)した際は、「デシ!」と犬を呼ぶように呼び捨てをくらう。私はこの呼ばれ方にすごく傷つき、やりきれなさを伴う虚(むな)しさが込み上げてくる思いを経験したのでした。住職として日曜学校を荷負(にお)おうとしているのに、私の思いとは反し、「認めてもらえない存在」という烙印(らくいん)を子どもたちに押されたようで大変落ち込みました。
米沢師は寄稿文の中で、「私たちのもっとも捨てがたいものは、(中略)自惚(うぬぼれ)ごころでありますが、(中略)これを捨て得たとき、もっとも大切な願いである、心やすらかな真実の国へ生まれる」とも書いておられます。虚しさを感じたということは、自身の自惚れに気づき、本当の自身の姿を知る機会であったのです。私においては、「デシ」と呼ばれることの虚しさとは、他者(子どもたち)に尊厳を見出すことができない状況で、自尊心という名の我が身の可愛さでしかありませんでした。つまり、そこには他者がいるにもかかわらず他者存在が欠落していたのです。他者を尊厳ある人と見出せた時こそ、心安らかなる真実の国へ生まれ、「不真実」と如来より言い当てられた私の歩みが始まります。
子どもたちが尊き他者としてこの私に迫ってきて22年、今も日曜学校は続いています。お互いを丸ごと認め、そして我が身自身を知らされる場が日曜学校でした。それはどこまでも、「他と比べることのない尊いいのちの場を今ここに開いてゆきたい」との願いを宿すと同時に、自分の至らなさを気づかせていただく道場でもあったのです。
芳原 里詩(よしはら さとし)
1963年生まれ。小松大聖寺教区第1組妙德寺住職。
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
◎先月から急に季節が変わり冬らしくなってきました。今月はもう師走です。光陰矢のごとしと言いますが、今さらながら時間の経過に驚きます。今年は元日に能登半島震災が起こり暗澹(あんたん)たる幕開けでした。また夏にはパリオリンピック・パラリンピックがあり日本人選手の活躍が報道されました。記録的な猛暑も各地で観測されました。うれしいことも悲しいこともありましたが阿弥陀さまの願いの中で生かされていることに感謝したいと思います。
一年間大変お世話になり、ありがとうございました。どうぞよいお年をお迎えください。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
合掌

2024年11月の法話
|
[11月の法語] |
|
仏の救いのはたらきが 私の声となったお念仏 |
|
Our voices saying the Buddha-name nenbutsu |
|
内藤知康(ないとうともやす) |
[法話]
2022年4月25日に、恩師の丘山新先生がご往生された。大学3年生時からご指導くださっていたので35年以上に及ぶお付き合いをいただいたことになる。最初は大学時代、続いて親鸞聖人の和語聖教勉強会、そして京都にいらしてからは本願寺派総合研究所にてご指導を賜(たまわ)った。
先生は勉強会を「最近、何か面白いことがありましたか?」という質問で始める。不用意なことを言うと、つまらなさそうにされるので要注意だ。東京で和語聖教(わごしょうぎょう=親鸞聖人が和文で綴(つづ)られた著作)の勉強会をしていた時には、東京教区のA先生が、いつも面白いことを言ってくれたので、研究会が盛り上がった。A先生の意見は、素朴だが核心を突く問題提起が多く、丘山先生はそういう話題を好まれた。小賢(こざか)しくなるなという戒(いまし)めがあったように思う。
先生自ら面白い気づきを披露(ひろう)されることもある。その一つを紹介したい。
「最近は、善いことをしようとする心が起きると、その心は誰かから頂戴(ちょうだい)したと思うようにしているんだ。たとえば、電車で席を譲ろうという心が生まれたら、この心は、誰からもらったかな、と考えるんだ。過去世(かこぜ=現世に生まれる前に存在していた過去の世)に仏さまから頂戴したものかもと思ったりするんだ。どう思う、藤丸さん」
20年くらい前のことだ。この時、私はピンとこなかった。しかし、今思うと、非常に大事な問題提起だった(先生の言葉は、10年後に効(き)いてきたりする)。
先日も甥(おい)っ子が、不承不承(ふしょうぶしょう=気が進まないままにするさま)「ごめんなさい」と言いに来た。本堂の障子(しょうじ)を破ったのが一つ目の理由。二つ目は、母親に「謝ってきなさい」と言われたからだ。これは母親に促(うなが)された謝罪である。この謝罪が、誰によるものかは明確だ。
このように、現在の誰かによって直前に促された行為は「誰によるもの」かがわかりやすい。ところが、遠い過去に由来し、時間を超えて促されたものはわかりにくい。仏教には「薫習(くんじゅう)」という言葉がある。ある行為が、香りがたきしめられるように心に留まり、時間を経て影響が出るという意味だ。
こうした場合、何に影響を受けて現れ出たか気づきにくい。自分の心が起こしたくらいにしか考えないから、由来を尋ねない。親鸞聖人は、
「たまたま信心を獲(え)ば、遠く宿縁(しゅくえん)を慶(よろこ)べ」(『浄土文類聚鈔』、『註釈版聖典』484頁)
とおっしゃった。信心をいただいたなら、ずっと前にあった過去からの原因を慶びなさいというお言葉だ。
そもそも、私たちの行為で、何からも影響を受けていないものはない。では私の声として出てくるお念仏は、どこから来たのだろう。源(みなもと)は阿弥陀さまが菩薩として願を立てた時にあり、多くの人々の信心、念仏の声を通して私のところにやって来た。その由来を聞くのが、聞法である。由来を尋ねさせていただくと、仏さまの慈(いつく)しみと念仏に生きた懐かしい方々の願いが香ってくる。
藤丸 智雄(ふじまる ともお)
武蔵野大学非常勤講師、岡山理科大学非常勤講師、
前浄土真宗本願寺派総合研究所副所長、兵庫教区岡山南組源照寺住職
本願寺出版社(本願寺派)発行『心に響くことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
◎先月初旬は30℃前半だった最高気温がようやく20℃前半くらいになり秋らしくなりました。いつまでこんな暑い日々が続くのかとうんざりしていた時期もありましたが、どんなことにも終わりがあることを再確認しました。しばらくは寒暖の差が大きいのでくれぐれもご自愛くださいますようお念じ申し上げます。
合掌

2024年10月の法話
|
[10月の法語] |
|
人間が人間だけでやっていく 現代の問題はそこにある |
|
Humans think only of what is good for humans. That is the problem of the modern age. |
|
安田理深 |
[法話]
私が仏法の聴聞(ちょうもん=法話、説教などを耳を傾けて聞くこと)の場に初めて出向いたのは、30代に差し掛かる頃でした。当時、幼馴染(おさななじみ)を自死で失い、途方(とほう)に暮れ、居ても立っても居られなかったのがきっかけでした。
初めて訪ねた場は、部屋いっぱいに聞法者(もんぽうしゃ)が集まっており、皆で「正信偈(しょうしんげ)」をお勤めし、静かに語る宗正元(そうしょうげん:1927~ 真宗大谷派僧侶)先生の姿があり、先生の話を熱心に聞く方々の姿がありました。その熱気に満ちた光景に、「このような場所があったのか」と驚かされたことを今でも鮮明(せんめい)に思い出します。
その場で先生がお聖教(しょうぎょう)の言葉を語られる時、言葉そのものを説明するというものではなく、様々な表現をもって語ってくださるというものでありました。
その中でも心を打たれたのは、先生が『目連所問経(もくれんしょもんきょう)』の、
たとえば万川長流(ばんせんちょうる)に草木(そうもく)ありて、前は後を顧(かえり)みず、後は前を顧みず、すべて大海に会(え)するがごとし。世間もまたしかなり。豪貴富楽(ごうきふらく)自在なることありといえども、ことごとく生老病死を勉(まぬか)るることを得ず。
(=たとえば、長い川の流れに漂う草木は、前のものが後のものを気にかけることもなく、後のものが前のものを気にかけることもなく、すべて大海に流れこむようなものである。世間のありさまもその通りで、身分が高く豊かで何不自由ないものでも、すべてのものはみな生老病死の苦を免(まぬが)れることはできない)
(『真宗聖典』173頁)
という文を取り上げた後におっしゃった、「人生は途中。一生涯は途中である」という言葉でした。その言葉を聞いた私は、幼馴染の人生も、私の人生も途中であり、それまで人生とは人それぞれに終えていく、完結していくものだと思っていたので、そのスケールの大きさに驚かされました。またそれは深く長く広がった人間の歴史的な歩みということへの頷(うなづ)きであったのだと思います。
先生の語ってくださる言葉の中には、曽我量深(そがりょうじん:1875~1971真宗大谷派僧侶、仏教思想家)、金子大榮(かねこだいえい:1881~ 1976真宗大谷派僧侶、仏教思想家)、安田理深(1900~ 1982日本の仏教学者)他数々の先生たちの言葉がありました。その中で気づかされたのは、先生の言葉は、ご自身が人生において聴聞してこられた諸師の言葉であり市井(しせい=人が多く集まり住む所)の方々の言葉でありました。そしてそれは先生の背景からの私たちへの呼びかけの言葉であります。歴史の叫び、苦悩の歴史の中で苦闘しながら現実を受け止めて生み出されてきた言葉であると、私は受け止めております。
しかし、私自身の日常に目を向けると、身に起こる問題に対し解決ばかりを求めています。結論を急ぎ、分かりやすさの中に自らを安心させてくれる答えをスマートフォンで探すのに必死です。先に受け止め頷いたことも虚しく、日常の中で私自身の安心が最優先です。安田先生は、このような在(あ)り方は現実を拒(こば)む姿なのだと教えてくださいます。
一方で目立たず、お聖教の言葉の理解の別を超え、身の現実に顔を上げ法と向き合う方々がいる情熱の場があります。そのことを知りながらも、そうした場になかなか足が向かない私に、安田先生は冒頭の法語に続けて言われます。
理性に立った人間が理性にいきづまる。現代自身が大きな危機にいる。法というものと遊離(ゆうり=他と離れて存在すること)した社会、歴史的現実と離れた時に仏法は死んだのである。(『聞思の人⑤安田理深集(上)』東本願寺出版)
私と仏法との距離について考えさせられます。そして、そのたびに「とにかく座っていればいい」という私の恩師・大島義男先生からの言葉が耳鳴りのように頭に響き、私を安眠させてくれません。この煩(わずら)わしく思う耳鳴りこそ私に呼びかけてくる仏法なのかもしれません。
林 法真(はやし のりまさ)
1982年生まれ。東京教区長野2組西永寺衆徒
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。