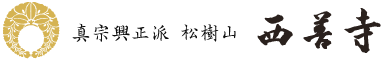2026年2月の法話
|
[2月の法語] |
|
一切衆生の救われる道でなければ 自分は救われない |
|
If thre is not a way to save all life, then there is no way for me to be saved. |
|
金子 大榮 |
[法話]
この法語に見られる「自分」という言葉には、大きく分けて二つの立場を想定できます。そして、その立場によって法語の意味も少し変わってくるような気がします。
一つは、親鸞聖人が非常に大切にした『仏説無量寿経』という経典に出てくる法蔵菩薩の立場です。法蔵菩薩はのちに阿弥陀仏と成りますが、成仏する前に生きとし生けるもの(一切衆生)を救う願いを立て、「願いが実現しなければ自分は仏に成らない」と誓います。これは、法蔵菩薩にとって一切衆生の救済が成仏の絶対条件であることを意味します。
つまり、法蔵菩薩の立場から言えば、この法語は「あらゆる存在が救われないことには「自分」も救われない」という断固たる決意、あるいは救いの構造を表す言葉になります。
もう一つは、「煩悩具足の凡夫」と言われるような、自己中心的な欲望に縛られて生きる平凡でありふれた者の立場です。親鸞聖人は、まさしく自分が「煩悩具足の凡夫」であることを自覚して、ただ念仏すること以外に助かる道はないと言います。それは「いずれの行もおよびがたき身」と言われるように、いかなる修行も「煩悩具足の凡夫」には成し遂げ難いことを痛感したからに他なりません。特に念仏以外の修行は個人の素質や能力を当てにするため、「煩悩具足の凡夫」を救えるだけの平等性・普遍性(ふへんせい=すべてのものに通じる性質。また、広くすべての場合にあてはめることのできる性質)を持ち得なかったのです。
このように、少なくとも親鸞聖人が立った「煩悩具足の凡夫」の立場から言えば、「あらゆる存在に平等普遍に成り立つ道でなければ「自分」という存在は救いようがない」とも読めます。
そもそも、金子氏が表題の言葉を語った文脈では、明らかに前者の意味です。金子氏は、美しい花を愛でるにも、その感動を共に分かち合う相手がいなければ美しさを味わえないことを例に挙げ、喜びや悲しみは決して個人的な問題に収まらないのだと言います。
確かに私たちは日常の様々な場面で、喜びを共有できる相手が多いほど、より大きな喜びを感じたことがあるはずです。また、悲しみの原因がより多くの人に関わるものであるほど、より深刻に感じられたこともあるでしょう。その意味で、「自分」一人の救いを良しとしない一面は、誰しも本来的に持っているのかもしれません。
しかし一方で、状況次第で「自分さえ良ければ」と自分本位の考え方を優先することも少なくありません。それどころか他人の失敗や不幸を喜ぶことさえあります。このことは、私たちにとって「他人の不幸は蜜の味」という言葉が聞き慣れたものである程度には、心理的傾向として往々(おうおう=しばしば)に有り得ると言えるでしょう。
そこであらためて法蔵菩薩の立場で考えてみると、私たちは「一切衆生」と呼ばれる救いの対象をどこまで押し広げることができるでしょうか。家族や友人ならともかく、悪の限りを尽くしてきたような人、さらには人類以外の生き物はどうでしょうか。そしてこのように考えていくと、私たちは救われるべきでない、あるいは、その救いに無関心な存在にどうしても思い至るのではないでしょうか。
ここに私たちの考えるべき方向の転換点があります。思えば親鸞聖人は、まず自分自身がどのような人間なのかに目を向け考え直した人でした。すると見えてきたのはどうにも救いようのない「煩悩具足の凡夫」、「いずれの行もおよびがたき身」としての「自分」です。しかしだからこそ親鸞聖人は、その「自分」をも救おうとする法蔵菩薩の願いを全存在の内なる願いとして聞き、そこに確証された世界を「一切衆生の救われる道」として示し続けたのでしょう。
松岡 淳彌(まつおか じゅんじ)
1990年生まれ。大谷大学任期制助教。
九州教区長崎組安樂寺衆徒。
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註]金子大榮:(1881~1976)日本の明治~昭和期に活躍した真宗大谷派僧侶、仏教思想家。前近代における仏教・浄土真宗の伝統的な教学・信仰を、広範な学識と深い自己省察にもとづく信仰とによって受け止め直し、近代思想界・信仰界に開放した。