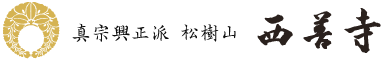2025年7月の法話
|
[7月の法語] |
|
老いや病や死が人生を輝かせてくださる |
|
Aging, illness, and death enables life to shine. |
|
湯浅 成幸 |
[法話]
東雲(しののめ=東の空がわずかに明るくなる頃、あけがた)の空に生まれたばかりの太陽も、一日の終わりには西の彼方(かなた)へ沈(しず)んでゆくように、人もまたこの世に生を受けたならば、必ずその命を終えるときを迎(むか)えます。桃のような頬(ほお)のかわいらしい赤ちゃんも、やがて大人になるように、すべてのことは刻々と変化して移り変わっていきますが、同じ変化でも老いや病や死の現実は受け入れがたいものがあります。特に死を予感させるような病や生きていることに空(むな)しさを感じるような出来事に遭(あ)ったとき、「なぜ自分はこの世に生まれてきたのだろうか」「人生に意味などあるのだろうか」という問いが心の中に去来(きょらい)することでしょう。果たして私自身はこの問いにどのように向き合えるのだろうか。老病死の身を引き受けなければいけない事実は、人として生まれたからには誰一人避(さ)けられない問題です。
表題の「老いや病や死が、人生を輝かせてくださる」という言葉の前には「私たちにとっては、老いも病も死も、除(のぞ)かれるもの、不幸なことではなく、老病死によって生の豊かな営(いとな)みを教えられるわけです」という一文があります。「老いや病や死が、人生を輝かせてくださる」とはどういうことなのでしょうか。私はこの言葉を初めて聞いたとき、一昨年の秋に闘病中の母と交(か)わした言葉を思い出しました。
2022年の晩夏に体調を崩(くず)した母は、病院での検査の結果、投薬治療を行うことになりました。二回目の投薬のために入院する際、待合室で一緒に座っていたときのことです。当時はコロナ下にあり、家族は病室へ入ることができず、しばしの別れに不安と寂しさを感じていました。そのとき母は、「74歳になって、この年まで生きてこられて良かった。お父さんと結婚して、子どもも生まれて、孫にも会えて良かった。精いっぱいに生きてきたから悔(く)いはない」と、そして後に続く言葉は、生き死には阿弥陀さんにお任(まか)せして治療に向かうと語っているように聞こえました。
治療によってもし病が癒(い)えて体に力が戻ったら、母の願いはもう一度台所に立って料理をすることでした。ささやかな日常こそもう一度取り戻したいかけがえのない大切なものであることを教えられ、一緒に泣き笑いして過ごしたたくさんの時間が一瞬の出来事のように感じられました。親子として濃密に過ごした日々に生じた様々な感情も、母を看取(みと)るまでの間に解きほぐされ、母に「ありがとう」「ごめんね」と伝えると「こちらこそ」と返事をくれて、お互いにゆるし合う時間が持てたのもまた、かけがえのないことでした。
人間の眼からは、老病死や人生の挫折(ざせつ)は何としても避(さ)けたいことに思われます。しかし、人生を海に、仏の智慧や慈悲をお日さまと譬(たと)えるならば、命の終わる頃、黄昏時(たそがれどき=夕焼けで薄暗い中、景色が黄金色に輝く時間帯)の海は夕日に照らされ金色に輝き、その豊かさと美しさを知ることのできる大切な時間なのではないでしょうか。
別れは悲しい、けれども悲しいと同時にその人の存在と人生とは尊いものであることを知らされる大事な機会であるように思われます。
立島 直子(たつしま なおこ)
1975 年生まれ。富山教区第1組稱名寺衆徒
東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載
※ホームページ用に体裁を変更しております。
※本文の著作権は作者本人に属しております。
[註]湯浅 成幸:1930年熊本県生まれ。真宗大谷派山田寺前住職。
現在、熊本刑務所教誨(きょうかい)師。篤志(とくし)面接員
◎暑い日が続いています。先月後半には早くも梅雨明け宣言がなされました。年々暑い時期が長くなっているような気がします。くれぐれも熱中症には気をつけてお過ごし下さい。
合掌